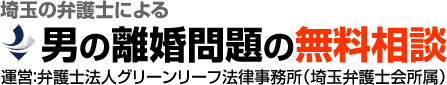紛争の内容
婚姻以来家計管理を配偶者に任せてきた、配偶者から離婚を切り出されたタイミングで返却された自身の預金口座の残高をみると僅かな金額しか残されていない状態であった、配偶者は離婚調停を起こし自身の財産についてはほとんどが親の遺産であると主張している、とのご相談でした。
ご相談者様の財産が配偶者のもとに流れている可能性が高いとのことでしたので、調停事件の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
調停において互いの財産資料の開示が行われました。
配偶者から開示された口座関係資料を確認したところ、ご相談者様の口座と配偶者の口座間で度重なる預金移動が行われていたため、なぜこのような経過となったのかについて配偶者側に確認を行いました。
別途、配偶者は自身の財産の大半は親の遺産であると主張していたため、その根拠を示すよう資料の開示を求めましたが、配偶者は十分な資料が提出できない状態でした。
調停の終盤に配偶者から500万円弱の財産分与を行うという離婚条件が提示されましたが、ご相談者様はやはり納得できないということで調停は不成立として訴訟で争うことになりました。
訴訟では財産分与を中心とした審理が行われました。
裁判所からは配偶者が主張する特有財産については資料がない部分が多いためあまり認めることはできないとの心証が開示されました。
和解協議を経ましたが、ご相談者様はここまで来たので判決がどうなるのか確認したいとのことでしたので、和解協議は打ち切り判決をもらうこととしました。
本事例の結末
判決では配偶者の特有財産の主張の大半が認められず、配偶者に対して財産分与として700万円余の支払いを命じるという内容となりました。
判決確定後、配偶者から判決記載の金額を回収し事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
家計管理を一方に委ねていると家計収入がどのように管理されているかよく分からないという事態に陥ることがままあります。
管理していた側はそこまで残っていないと主張し、管理を任せていた側はもっと残っているはずだと主張することになりますが、財産がどこにどのような形で残っているかを示せない限り、裁判になった場合には財産があるとは認められないという結論になりがちです。
家計管理を配偶者に委ねているという場合には適宜のタイミングで財産がどのような形で管理されているかを確認することで双方の財産に関する認識を統一しておくことが後の紛争を避けるために重要になってきます。
弁護士 吉田 竜二