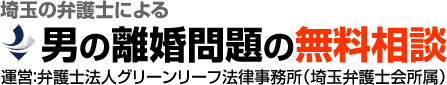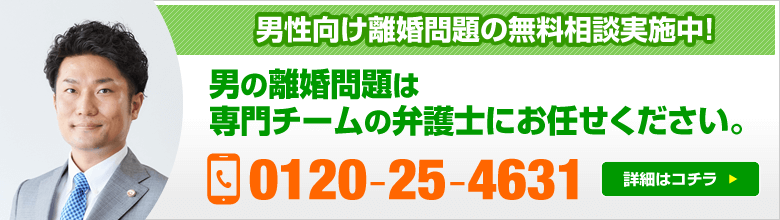離婚訴訟を行っている方へ。
相手方が財産開示に応じない場合などには、文書調査嘱託という方法があります。
文書調査嘱託とは?
文書調査嘱託とは、当事者の一方から、家庭裁判所に財産等の調査をするようにお願いをして、家庭裁判所が許可すれば、家庭裁判所から嘱託先(金融機関など)に調査を依頼する手続です。
裁判所を介する手続であることから、正確な回答が返ってくる可能性が高く、財産などを調査する際に重宝します。
文書調査嘱託のメリットは?
この手続のメリットは、裁判所の手続であることから、個人情報などを理由に回答を拒絶される可能性が乏しく、正確な情報を収集できることです。
文書調査嘱託のデメリットは?
一方、デメリットは、裁判所が相手方の意見を聞き、最終的には裁判所が採否を判断しますので、例えば網羅的・探索的な調査(例えば、A銀行に、Yさんの口座をどこの支店にあるかを調べて開示するように求める等)は否決される可能性が高く、具体的に財産調査の嘱託先を特定し、その必要性を分かってもらうことが必要です(例えば、B銀行C支店に、被告名義の口座番号1234567について必要な期間の取引履歴の開示を求める等)。
また、求釈明(相手方に任意の回答を求める主張等)を行うなどして段階を踏んで、それでも相手方が回答を拒絶するなどして、裁判所から嘱託先に調査をする必要性がある状況でなければなりません。
文書調査嘱託の具体的な流れは?
なお、具体的な、調査嘱託を進める流れは以下のとおりです。
大まかに、2カ月程度は手続に時間を見ておいた方が無難です。
①求釈明により回答が得られない
⇓
②裁判所に調査嘱託を申し立てる
⇓
③裁判所は相手の意見を窺う
※これにより調査嘱託の有無、内容に争いが生じたら、双方が意見書等を出し合う
※意見はきちんと説得的に説明する必要がある
⇓
④裁判所が採否を決定する
⇓
⑤裁判所が採用した場合、嘱託先に郵便で問い合わせる
※回答まで、約1ヵ月の時間がかかる
⇓
⑥嘱託先から裁判所に回答が届く
⇓
⑦回答を閲覧謄写するために、私から裁判所に書類の謄写を依頼する
※実費がかかります
⇓
⑧謄写した記録が届くので、この段階で初めて回答を知ることができる
⇓
⑨証拠として提出する必要があれば、当事者が証拠として提出する
という流れです。
この手続は、離婚調停の段階でも利用できますが、相手方が拒否すると難しいと考えます。
よって、離婚裁判で用いる手続であると覚えておいていただくとよいです。